検索窓に「サントリー ホワイト」と打ち込むと、真っ先に「まずい」という言葉が目に飛び込んでくる。
これからウイスキーを楽しみたいと考えている方、あるいは日々の晩酌の選択肢として検討している方にとって、これほど購入をためらわせる言葉はないでしょう。
「安かろう悪かろうの商品なのではないか」「買って後悔したらどうしよう」そんな不安が頭をよぎるのも無理はありません。
しかし、このウイスキーが日本のウイスキー史の幕開けを飾った、記念碑的な一本であることをご存知でしょうか。
これほど長い歴史を持ちながら、なぜ今なおネガティブな評価が語り継がれるのか。
この記事では、その根深い噂の真相から現代における真の評価まで、あらゆる角度から徹底的に掘り下げていきます。
本稿では、単に味の感想を述べるに留まりません。
まず、そもそもウイスキーって何?という基本的な知識から丁寧に解説し、その上で、日本初の国産ウイスキー「ホワイト」とは?という、その輝かしい誕生の物語と、発売当初につまずいてしまった歴史的背景にまで深く迫ります。
さらに、インターネット上で囁かれる「サントリーホワイト 終売」の噂は本当かという真偽を明らかにし、そして最も気になる、肝心の味は?というサントリーホワイトの風味評価について、様々な客観的なレビューの傾向を分析しながら詳しく紹介します。
加えて、サントリーホワイトの価格とコストパフォーマンスを冷静に分析し、誰もが知る定番「角瓶」との違いや、兄弟のような存在である「レッド」との違いは何ですか?といった具体的な比較を通じて、ホワイトならではの個性と確固たる立ち位置を明確にしていきます。
また、近年「なぜ白州は売ってないのか」と話題になる品薄問題にも触れ、それとは対照的なホワイトの安定供給の理由を探ることで、その存在価値を再評価。
豆知識としてサントリーの最上級ウイスキーの世界を覗き見つつ、最終的には、なぜサントリーホワイト ハイボールが最高の飲み方と言えるのか、その理由と美味しい作り方まで具体的にお伝えします。
この記事を最後までお読みいただければ、単に「まずいかもしれない」という漠然とした不安は解消されているはずです。
そして、サントリーホワイトを自信を持って選び、その歴史に裏打ちされた個性を最大限に楽しむための知識が、きっと身についていることでしょう。
記事のポイント
- サントリーホワイトが「まずい」と言われた歴史的背景
- 現在の風味や評価、他のウイスキーとの明確な違い
- 価格や販売状況、コストパフォーマンスの実際
- まずさを感じさせない美味しい飲み方とアレンジレシピ
サントリーホワイトは本当にまずい?噂の真相と歴史
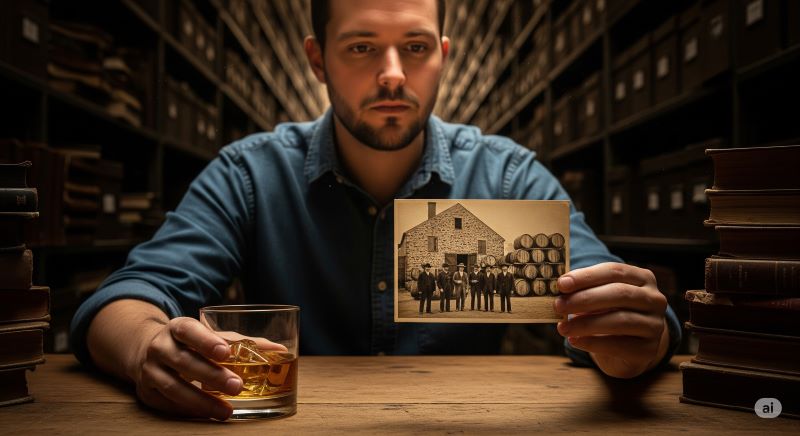
ウイスキーガイド イメージ
この章では、サントリーホワイトが「まずい」と言われるようになった歴史的背景を解説します。
日本初のウイスキーとしての誕生秘話から、現在の風味、価格、そして終売の噂の真相まで、基本的な情報を網羅的に知りたい方はぜひ参考にしてください。
ポイント
- そもそもウイスキーって何?基本を解説
- 日本初の国産ウイスキー「ホワイト」とは?
- 「サントリーホワイト 終売」の噂は本当か
- 肝心の味は?サントリーホワイトの風味評価
- サントリーホワイト 価格とコストパフォーマンス
そもそもウイスキーって何?基本を解説

ウイスキーガイド イメージ
ウイスキーについて深く知る前に、まずその定義から確認しておきましょう。
ウイスキーとは、非常にシンプルに言えば、大麦やライ麦、トウモロコシといった穀物を主原料として造られる蒸溜酒の一種です。
製造工程は複雑ですが、基本的には穀物のでんぷんを糖に変え(糖化)、酵母の力でアルコール発酵させ、それを蒸溜器で蒸溜してアルコール度数を高め、最終的に木製の樽で寝かせる(貯蔵・熟成)ことで完成します。
日本の酒税法では、ウイスキーは「発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、酵母により発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの」とその製法が定義されています。
(出典:e-Gov法令検索 酒税法)
この製造工程の中でも、ウイスキーの個性を決定づける最も重要な要素が「樽での熟成」です。
蒸溜したてのウイスキーの原酒は「ニューポット」や「ニュースピリッツ」と呼ばれ、無色透明で荒々しい味わいをしています。
これがオーク材などで作られた樽の中で長い年月を過ごすうちに、樽の成分が溶け出し、ゆっくりと呼吸をすることで酸化が進み、私たちが知る美しい琥珀色と、バニラやカラメルのような複雑でまろやかな香味を持つ液体へと変化していくのです。
ウイスキーの主な種類
一口にウイスキーと言っても、その種類は多岐にわたります。
ここでは代表的な分類をいくつか紹介します。
まず、原料による分類が基本となります。
大麦麦芽(モルト)のみを原料とし、単式蒸溜器という伝統的な銅製の釜で蒸溜されるものを「モルトウイスキー」と呼びます。
これは製造に手間がかかり、豊かな香りと複雑な味わいを持つのが特徴です。
一方で、トウモロコシや小麦などの穀類を主原料とし、連続式蒸溜器で効率的に蒸溜されるのが「グレーンウイスキー」です。
こちらはクセが少なく、クリアで穏やかな味わいになります。
そして、この個性豊かなモルトウイスキーと、穏やかなグレーンウイスキーを複数種類ブレンドして、バランスの取れた味わいを創り出したものが「ブレンデッドウイスキー」です。
今回解説するサントリーホワイトも、このブレンデッドウイスキーに分類されます。
さらに、生産地によっても大きく分類され、特に有名なのが「世界五大ウイスキー」です。
1:スコッチウイスキー(スコットランド)
スモーキーな香りを持つものから華やかなものまで、非常に多様な個性で知られます。
2:アイリッシュウイスキー(アイルランド)
伝統的に3回蒸溜されることが多く、滑らかで軽やかな味わいが特徴です。
3:アメリカンウイスキー(アメリカ)
トウモロコシを主原料とする「バーボン」が有名で、焦がした樽由来の甘く力強い香りを持ちます。
4:カナディアンウイスキー(カナダ)
ライ麦を主に使用することが多く、軽快でクセのないスムーズな飲み口で知られます。
5:ジャパニーズウイスキー(日本)
スコッチウイスキーの製法を参考にしつつ、日本人の繊細な味覚に合わせて造られ、非常に丁寧でバランスの取れた味わいが国際的に高く評価されています。
このように、原料や製法、産地の違いが絡み合い、驚くほど多様な個性が生まれるのがウイスキーの奥深い世界なのです。
この基本を理解しておくことで、サントリーホワイトがどのようなウイスキーなのかが、より明確に見えてくるでしょう。
日本初の国産ウイスキー「ホワイト」とは?

ウイスキーガイド イメージ
サントリーホワイトは、単なるウイスキーの一銘柄という言葉では片付けられない、日本の洋酒史における金字塔的な存在です。これは、1929年(昭和4年)にサントリーの前身である壽屋(ことぶきや)から発売された、日本初の本格的な国産ウイスキーに他なりません。 (出典:サントリーの歴史 1899年〜) リンク先:https://www.suntory.co.jp/company/history/timeline/
その誕生は、サントリー創業者である鳥井信治郎の「日本人の繊細な味覚に合った、世界に誇れるウイスキーをこの手で造りたい」という燃えるような情熱から始まりました。
まだ洋酒文化が一般に根付いていなかった時代に、ウイスキー事業に乗り出すことはあまりにも大きな挑戦であり、周囲からは無謀だと反対されました。
しかし、彼の「やってみなはれ」の精神が、この壮大な夢を実現へと突き動かしたのです。
山崎蒸溜所の設立と二人のキーパーソン
本格的なウイスキー造りのため、鳥井はまず、ウイスキー造りに不可欠な良質な水を求めて日本全国を探索しました。
そして1923年、名水百選にも選ばれるほどの水が湧き出る、京都郊外の山崎の地に日本初のモルトウイスキー蒸溜所「山崎蒸溜所」を設立します。
さらに彼は、ウイスキー造りの責任者として、単身スコットランドに渡り本場の製造技術を学んできた竹鶴政孝(後のニッカウヰスキー創業者)を初代工場長として招聘しました。
ブレンドによる多彩な味わいを重視する鳥井と、原酒そのものの品質をどこまでも追求する竹鶴。
二人の天才がそれぞれの信念をぶつけ合いながら、日本のウイスキーの黎明期を築き上げていったのです。
華々しいデビューと厳しい評価
数々の試行錯誤の末、ついに1929年4月1日に「サントリーウヰスキー」が発売されます。
その白いラベルデザインから、愛飲家の間では親しみを込めて「白札(しろふだ)」と呼ばれるようになりました。
この愛称が、後の「サントリーホワイト」という製品名に繋がっていきます。
当時の価格は1本4円50銭。大学出の初任給が70円ほどだった時代、非常に高価な贅沢品であり、大きな期待と共に世に送り出されました。
しかし、その評価は惨憺たるものでした。
本場スコットランドの製法を忠実に再現することにこだわった結果、当時の日本人にとってはピート(仕込みに使う麦芽を乾燥させる際に焚く泥炭)由来のスモーキーな香りが強烈すぎ、「焦げ臭い」「煙たい飲み物」と酷評されてしまったのです。
言ってしまえば、本格的すぎたことが、かえって大衆に受け入れられない皮肉な結果を招きました。
この発売当初の強烈なネガティブイメージこそが、後世まで「サントリーホワイトはまずい」という噂の源流になったと考えられます。
もちろん、サントリーはこの失敗に屈しませんでした。
この教訓をバネに、翌年にはより日本人の味覚に合わせた「赤札(現在のサントリーレッド)」を発売して成功を収めます。
そしてホワイト自体も、時代の変遷と人々の味覚の変化に合わせて、発売以来、数えきれないほどの改良が重ねられてきました。
当初の荒々しい個性は、現代のまろやかで飲みやすい味わいへと進化を遂げ、今もなお歴史の生き証人として私たちの前にあり続けているのです。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
「サントリーホワイト 終売」の噂は本当か

ウイスキーガイド イメージ
結論から申し上げますと、インターネット上で時折見かける「サントリーホワイトは終売になった」という噂は、明確に誤った情報です。
2025年8月現在、サントリーホワイトは終売になっておらず、サントリーの公式ウェブサイトにも定番商品としてしっかりと掲載されています。
全国の酒店やスーパーマーケット、オンラインストアでも、640mlの瓶から大容量のペットボトルまで、様々な形態で広く販売が継続されています。
(出典:サントリーウイスキーホワイト 製品紹介)
では、現役で販売されているにもかかわらず、なぜこのような終売の噂が後を絶たないのでしょうか。
それにはいくつかの複合的な理由が考えられます。
噂が生まれる背景
他の「白いウイスキー」との混同
最も大きな理由として挙げられるのが、同じサントリーから発売されていた他の商品との混同です。
特に、2019年に一度休売となった「サントリーウイスキー白角」の存在が大きいでしょう。
「白角」は、その名の通り白い角瓶に入った商品で、「白」という共通のイメージから、その休売情報が「ホワイト(白札)も終売になった」という誤解を生んでしまった可能性が非常に高いです。
定期的なラベルデザインの変更
サントリーホワイトは非常に長い歴史を持つ商品のため、時代に合わせて何度かラベルデザインが変更されています。
昔のデザインに慣れ親しんだ方が、リニューアルされた新しいボトルを見て「以前のホワイトは無くなった(終売した)」と勘違いしてしまうケースも考えられます。
これは、長寿商品ならではの現象と言えるかもしれません。
店舗による取扱いの差
お近くのスーパーやコンビニエンスストアで見かけない、という経験から終売を疑う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これは店舗ごとの仕入れ方針によるものがほとんどです。
サントリーホワイトは、特に大容量ペットボトルなどは、業務用酒店や大型ディスカウントストアで安定して取り扱われる傾向があります。
一方で、店舗面積の限られるコンビニなどでは、より人気の高い「角瓶」などが優先され、ホワイトが置かれないことも少なくありません。
このように、店舗によって取扱いに差があることが、「売ってない=終売」という誤解に繋がりやすいのです。
これらの理由から、サントリーホワイトの終売説は周期的に浮上しますが、実際には日本のウイスキー史を支えてきた foundational な一本として、今もなお製造・販売が続けられている歴史ある現役のウイスキーです。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
肝心の味は?サントリーホワイトの風味評価

ウイスキーガイド イメージ
サントリーホワイトの味わいは、その歴史と同様に一筋縄ではいかない、非常に個性的なものとして知られています。
多くのテイスティングレビューで共通して指摘されるのは、まずその香り(ノージング)と味わいの第一印象です。
グラスに注いで香りを確かめると、まず感じるのは接着剤やシンナーにも似た、ツンと鼻を突くアルコール由来のアタックです。
これは熟成年数の若いスピリッツがブレンドされているためと考えられ、華やかな果実香や甘い樽香を期待すると、少し面食らってしまうかもしれません。
しかし、その刺激的な香りの奥を注意深く探ると、穀物由来のほのかな甘さや、青リンゴのような微かな酸味を感じ取ることもできます。
口に含んだ瞬間の味わいも、香りの印象と連動しています。
多くの人がまず感じるのは、舌の上をピリピリと刺激するシャープなアルコール感です。
特にストレートで飲むと、この若々しく力強いアタックをダイレクトに感じることになります。
ウイスキーを飲み慣れていない方や、まろやかな口当たりを好む方から「まずい」と評価されてしまう最大の要因は、おそらくこの点にあるでしょう。
しかし、その鋭い第一印象の後に、このウイスキーの真骨頂とも言える意外な特徴が現れます。
複数のテイスティングレビューによれば、刺激的なアルコール感が落ち着くと、まるで黒蜜やべっこう飴、かりんとうを思わせるような、濃厚でどこか懐かしい和の甘みがはっきりと立ち上がってくると評価されています。
(出典:ぴろのウイスキーブログ まずい?サントリーホワイトをレビュー!【意外と高評価】)
この素朴でしっかりとした甘みこそが、サントリーホワイトが持つ最大の魅力であり、多くのファンを惹きつけてやまない個性と言えます。
一方で、後味(フィニッシュ)には、漢方薬を思わせる独特の苦味や、湿った木材のようなニュアンスを感じるという意見もあり、この点が好みの分かれるところです。
余韻は比較的短く、味わいが口の中に長く留まることはなく、スッと消えていきます。
飲み方で変わるホワイトの表情
このように個性的な風味を持つサントリーホワイトは、飲み方によってその表情を大きく変えます。
ストレート
ホワイトの持つ刺激と甘み、その全てをダイレクトに感じられます。
このウイスキーの素顔を知るには最適な飲み方ですが、アルコール感が強いため、初心者の方にはあまりお勧めできません。
ロック
氷がゆっくりと溶けることでアルコールの角が取れ、ストレートよりも格段に飲みやすくなります。
隠れていた甘みが引き立ち、まろやかな口当たりを楽しむことができます。
水割り
加水することで香りがわずかに開きますが、元々の香味があまり強くないため、全体的に味がぼやけてしまい、水っぽく感じられる可能性があります。
水の量を慎重に調整する必要があります。
これらの点を総じて評価すると、サントリーホワイトはストレートやロックでじっくりと香味を分析しながら味わうタイプのウイスキーというよりは、何かと割ることでその真価を発揮する、ミキサーベース(カクテルの割り材)としての性格が非常に強いウイスキーであると言えるでしょう。
特に、次に紹介するハイボールとの相性は抜群です。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
サントリーホワイト 価格とコストパフォーマンス

ウイスキーガイド イメージ
サントリーホワイトが、発売から一世紀近く経った今もなお多くの人々に愛され続けている大きな理由の一つが、その一貫して手頃な価格設定にあります。
近年、ジャパニーズウイスキーはその世界的な人気から、特に熟成年数の長いボトルを中心に価格が高騰し続けています。
一部の有名銘柄が数十万円、あるいは数百万円で取引されることも珍しくない市場において、サントリーホワイトは日常的に楽しめる価格帯を頑なに守り続けているのです。
2025年8月時点の市場価格では、最も一般的な640ml瓶が1,000円前後で購入可能であり、これはウイスキー入門の一本としても、日々の晩酌用としても、非常に手が出しやすい価格と言えます。
(出典:サントリーウイスキーホワイト 640ml瓶 商品情報)
大容量ボトルに見る驚異的なコストパフォーマンス
サントリーホワイトの真価は、大容量のペットボトル製品のラインナップにおいて、さらに際立ちます。
業務用やヘビーユーザー向けに、1.92L、2.7L、4Lといったサイズが用意されており、これらは容量が大きくなるほど単価が安くなるように設定されています。
| ボトルサイズ | 市場価格(目安) | 100mlあたりの価格(目安) |
|---|---|---|
| 640ml(瓶) | 約1,100円 | 約172円 |
| 1.92L(ペット) | 約3,600円 | 約188円 |
| 2.7L(ペット) | 約5,000円 | 約185円 |
| 4L(ペット) | 約6,800円 | 約170円 |
※市場価格は2025年8月時点のものであり、販売店によって異なります。
上記のように、最も大きい4Lボトルを選べば、100mlあたりの価格は640ml瓶とほぼ同等か、それ以下になることもあります。
毎日ハイボールなどを楽しむ方にとっては、この大容量ボトルの存在が、家計の大きな助けとなることは間違いありません。
他の同価格帯のウイスキーと比較しても、そのコストパフォーマンスは非常に高い水準にあります。
例えば、同じサントリーの「角瓶」は700mlで1,500円以上することが多く、ホワイトはより手頃な価格帯に位置します。
ニッカウヰスキーの「ブラックニッカ クリア」とはほぼ同価格帯で競合しますが、どちらを選ぶかは味わいの好みによるところが大きいでしょう。
しかし、サントリーホワイトのコストパフォーマンスは、単なる価格の安さだけでは測れません。
前述の通り、これは「日本初の本格ウイスキー」という、日本の洋酒史の原点とも言える一本です。
その歴史的背景を持つウイスキーを、今なお1,000円前後で楽しめるという事実は、価格以上の大きな付加価値であると考えられます。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
まずい評価を覆すサントリーホワイト現在の魅力

ウイスキーガイド イメージ
この章では、サントリーホワイトの現在の魅力と比較を通じた立ち位置を解説します。
「角瓶」や「レッド」といった定番商品との違いから、最高の飲み方であるハイボールの作り方まで、このウイスキーを実際に楽しむための情報を知りたい方はぜひ参考にしてください。
ポイント
- 定番の「角瓶」との違い【サントリーホワイト】
- 兄貴分の「レッド」との違いは何ですか?
- なぜ白州は売ってない?ホワイトの安定供給
- 豆知識:サントリーの最上級ウイスキーは?
- サントリーホワイト ハイボールが最高の飲み方
- 結論:まずいと言われたホワイトの楽しみ方
定番の「角瓶」との違い【サントリーホワイト】

ウイスキーガイド イメージ
サントリーのブレンデッドウイスキーとして、ホワイトとしばしば比較されるのが、言わずと知れたロングセラー「角瓶」です。
どちらも日本のウイスキー史を語る上で欠かせない不朽の存在であり、同じ価格帯で棚に並んでいることも多いため、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。
しかし、その来歴や設計思想、そして香味のキャラクターは大きく異なります。
設計思想とブレンドの違い
最も大きな違いは、ブレンドされているウイスキーの構成と、その背景にある設計思想にあります。
先に誕生したホワイトが、手探りの中で本場スコッチに挑んだ挑戦的な一本であったのに対し、その8年後に発売された角瓶は、ホワイトの経験を糧に、より日本人の味覚に寄り添う「日本の洋食に合うウイスキー」として明確なコンセプトを持って開発されました。
この思想の違いは原材料に顕著に表れています。
角瓶が、サントリーの誇る山崎蒸溜所と白州蒸溜所のバーボン樽原酒をキーモルトとして贅沢に使用し、香味豊かなグレーンウイスキーとブレンドすることで、厚みとバランスを両立させているのが特徴です。
(出典:サントリーウイスキー角瓶)
一方、ホワイトは公式サイトの原材料表記によると、モルトウイスキーとグレーンウイスキーに加え、「グレーンスピリッツ」が使用されています。
これは香味を調整し、安定供給と手頃な価格を実現するための工夫であり、この違いが両者の個性を決定づけているのです。 (出典:サントリーウイスキーホワイト)
香りと味わいのキャラクターの違い
このブレンドの違いが、味わいのキャラクターに直結します。
角瓶のグラスを傾けると、まず感じるのはバーボン樽由来のバニラやハチミツを思わせる甘く華やかな香りです。
口に含むと、しっかりとしたコクと甘みがバランス良く広がり、最後はキレの良いドライな後口で締めくくられます。
この完成されたバランスが、ハイボールの王道として長年愛されている理由です。
対して、前述の通りホワイトは香りが穏やかで、華やかさよりもアルコールのシャープさが先に立ちます。
しかし、味わいの中盤から現れる黒蜜やかりんとうを思わせる、濃厚で少しビターな甘みは角瓶にはない、ホワイトならではの個性です。
言ってしまえば、角瓶が洗練された優等生だとしたら、ホワイトは無骨で素朴ながらも、芯の通った一本気な魅力を持つ存在と言えるでしょう。
どちらが良いというわけではなく、華やかでバランスの取れた味わいを求めるなら角瓶、シャープな口当たりと素朴で濃厚な甘みという、より強い個性を楽しみたいならホワイト、という選択ができます。
特にハイボールにした際のキャラクターの違いは明確で、ぜひ一度飲み比べてみることをお勧めします。
| 特徴 | サントリーホワイト | サントリー角瓶 |
|---|---|---|
| 発売年 | 1929年 | 1937年 |
| コンセプト | 日本初の本格ウイスキーへの挑戦 | 日本の食文化に合うウイスキー |
| 主要原材料 | モルト、グレーン、スピリッツ | モルト、グレーン |
| アルコール度数 | 40% | 40% |
| 香りの特徴 | 控えめ、シャープ、かすかな甘み | 華やか、バニラ、カラメル、オーク樽 |
| 味わいの特徴 | シャープな口当たり、濃厚でビターな甘み | 厚みのあるコク、バランスの取れた甘み |
サントリー ウイスキー 角瓶 40度 700ml
兄貴分の「レッド」との違いは何ですか?

ウイスキーガイド イメージ
サントリーホワイトの物語を語る上で、決して欠かすことのできないもう一つの存在が、ウイスキー「サントリーレッド」です。
ホワイトが発売された翌年の1930年(昭和5年)、壽屋は「サントリーウヰスキー赤札」として、この新しいウイスキーを世に送り出しました。
失敗から生まれた「弟分」
この二つのウイスキーの関係性は、単なる発売順序だけでは語れません。
前述の通り、社運を賭けて発売した高級品のホワイト(白札)は、あまりにも本格的すぎて市場に受け入れられず、会社を経営の危機に陥れました。
この大きな失敗から創業者・鳥井信治郎が得た教訓は、「日本人の舌はまだ、そこまでスモーキーなウイスキーを求めていない」ということでした。
そこで彼は、ホワイトの反省を活かし、ピート香を抑え、より日本人の味覚に馴染むようにブレンドを調整し、さらに価格も大衆向けにぐっと抑えた「赤札」を開発します。
これが大当たりし、壽屋の経営を救ったのです。
そのため、発売順で言えばホワイトが「兄貴分」ですが、市場での成功体験やその後のサントリーのウイスキー戦略の礎を築いたという意味では、レッドこそが重要な役割を果たしたと言えます。
ホワイトの挑戦があったからこそ、レッドの成功があったという、まさに兄弟のような関係性なのです。
味わいとキャラクターの違い
味わいの方向性にも、そうした開発経緯が色濃く反映されています。
アルコール度数がホワイトの40%に対し、レッドは39%とわずかに低く、より気軽に飲めるように設計されています。
香味の点では、レッドはホワイトよりもさらに淡麗で、クセのないクリアな口当たりと、キレのあるシャープな味わいが最大の特徴です。
ホワイトに感じられるような濃厚で個性的な甘みやコクといった要素は控えめですが、その分どんな割り方をしても味わいの邪魔をしない、ある種の「素直さ」を持っています。
複数のレビューでも、レッドは「より軽く、ドライである」と評価されています。
そのため、サントリーの低価格帯ウイスキーの中での棲み分けは非常に明確です。
少しでもウイスキーらしい甘みや歴史に裏打ちされた個性を感じたいのであればホワイト、一方で、ひたすらクリアな飲み口と、一杯あたりのコストを極限まで追求するのであればレッド、という選択ができるでしょう。
どちらも日本のウイスキーの歴史を体現する貴重な存在であり、その違いを知ることで、晩酌の楽しみ方が一層深まるはずです。
サントリーウイスキー レッド 39度 640ml 瓶
なぜ白州は売ってない?ホワイトの安定供給

ウイスキーガイド イメージ
近年、「白州」や「山崎」といったサントリーが誇るシングルモルトウイスキーは、定価で目にすることすら稀なほど、深刻な品薄で入手困難な状況が続いています。
ウイスキー愛好家はもちろん、これから楽しみたいと思っている方にとっても、この状況は大きな悩みの種でしょう。
シングルモルトが抱える「時間」という名の制約
この品薄の根本的な原因は、2000年代以降に日本のウイスキーが国際的なコンテストで数々の賞を受賞し、世界的な需要が予測をはるかに超えて爆発的に高まったことにあります。
特に、NHKの連続テレビ小説『マッサン』が放送された2014年以降、国内の需要も急増しました。
しかし、ウイスキーは製造に最低でも数年、長いものでは数十年という熟成期間を要する、まさに「時間」が造り上げるお酒です。
今日の需要を予測して、10年、20年前に生産量を増やしておくことは不可能であり、急な増産に全く対応できないのです。
さらに、日本のウイスキー市場は1980年代から長い冬の時代を経験し、多くの蒸溜所が生産量を大幅に削減していました。
その時期に仕込まれた原酒が、まさに現在の熟成期間10年以上の製品の元となるため、需要が爆発したときには、すでに原酒そのものが絶対的に不足しているという状況に陥ってしまったのです。
白州のような「シングルモルトウイスキー」は、その名の通り、単一(シングル)の蒸溜所で、大麦麦芽(モルト)のみを原料として造られた原酒だけで製品化されます。
他の蒸溜所の原酒を混ぜることができないため、その生産量は蒸溜所の規模と、そして何より現存する熟成原酒の量に完全に縛られてしまいます。
これが、白州が市場から姿を消してしまったかのように見える理由です。
サントリー 白州 NV 43% 100周年記念 蒸留所 ラベル 700ml箱付
安定供給を可能にするブレンデッドの技術
これに対して、サントリーホワイトが品切れになることなく安定して供給されているのはなぜでしょうか。
ここには、製品としての役割と、製造方法の違いが大きく関わっています。
ホワイトは、前述の通り「ブレンデッドウイスキー」に分類されます。
これは、個性豊かな複数のモルト原酒と、穏やかな性格のグレーンウイスキー、そして香味を調整するグレーンスピリッツを、ブレンダーと呼ばれる職人が絶妙な比率でブレンドして造られます。
特定の熟成年数の原酒だけに頼るのではなく、様々な特徴を持つ若い原酒から熟成した原酒までを巧みに組み合わせることで、味わいの骨格を保ちながら、大量生産に対応することが可能になります。
特に、香味の個性が穏やかなグレーンスピリッツを一部使用することは、味わいを軽やかにするだけでなく、希少なモルト原酒の使用量を調整し、製品全体の需給バランスを安定させる上で極めて重要な役割を果たしています。
これにより、サントリーホワイトは手頃な価格での安定供給を実現できているのです。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
これは決して製品の優劣を示すものではありません。
白州が「蒸溜所の個性を味わう」ための特別な一本であるならば、ホワイトは「いつでも変わらない味を、気軽に楽しめる」という日常に寄り添う役割を担っています。
それぞれのウイスキーが持つ、異なる価値と使命の違いと理解するのが最も適切でしょう。
豆知識:サントリーの最上級ウイスキーは?

ウイスキーガイド イメージ
サントリーホワイトのような日常的に楽しめるウイスキーから、世界中のコレクターが垂涎の的とする最高級品まで、サントリーが手掛けるウイスキーのラインナップは、驚くほど幅広いものです。
普段親しんでいるウイスキーとは次元の違う、その頂点の世界を少し覗いてみましょう。
芸術品の域に達した「山崎55年」
SUNTORY サントリー シングルモルトウイスキー 山崎55年
サントリーの最上級かつ最高額のウイスキーとして、世界にその名を知られているのが、伝説的なボトル「山崎55年」です。
これは、単に熟成年数が長いというだけではありません。
サントリーのウイスキー造りの歴史そのものを凝縮した、特別な一本です。
ブレンドには、サントリーの創業者・鳥井信治郎が1960年に蒸溜し、日本のウイスキーの父と子の想いを象徴するミズナラ樽で熟成された原酒と、二代目社長・佐治敬三の時代である1964年に蒸溜されたホワイトオーク樽原酒などが使用されています。
(出典:SUNTORY WHISKY 山崎55年)
創業家が三代にわたってブレンドの監修を手がけ、半世紀以上の眠りから覚めた原酒が織りなす香味は、伽羅を思わせる香木や熟した果実、そして長く続くビターな余韻が特徴とされます。
2020年に100本限定、定価300万円(税抜)で発売されましたが、その希少性と物語性から市場価値は瞬く間に高騰。
海外のオークションでは1億円近い価格で落札されるなど、もはや飲むためのお酒というよりも、後世に語り継がれるべき芸術品の領域に達していると言えるでしょう。
「響30年」に見るブレンディングの極致
サントリー 響30年 43度 700ml
もちろん、「山崎55年」はあまりにも特別な例です。
しかし、サントリーには他にも最高峰と呼ぶにふさわしいウイスキーが存在します。
その代表格が、ブレンデッドウイスキーの最高峰「響30年」です。
これは、サントリーが保有する80万個以上もの膨大な原酒の中から、酒齢30年以上のモルト原酒とグレーン原酒だけを、チーフブレンダーが厳選し、匠の技でブレンドした逸品です。
甘く華やかな香りと、重厚で深みのある味わい、そして驚くほど長く続く余韻は、サントリーが掲げる「ブレンドの美」の極致と言えます。
定価でも十数万円、市場では数十万円単位で取引されており、こちらも入手は極めて困難です。
このような最高峰のウイスキー造りにおいて培われた、原酒を見極める鋭い眼や、香味を最大限に引き出す繊細なブレンド技術、そして徹底した品質管理の哲学は、決して高級品だけに向けられたものではありません。
その知見や技術の一部は、サントリーホワイトのような日常的に楽しまれる製品の品質を安定させ、向上させるための礎となっています。
そう考えると、いつもの一杯の味わいが、より一層深く、価値あるものに感じられるかもしれません。
サントリーホワイト ハイボールが最高の飲み方

ウイスキーガイド イメージ
これまで見てきたように、サントリーホワイトはストレートで飲むにはやや個性が強く、好みが分かれるウイスキーです。
そのシャープな口当たりと独特の甘みは、まさに「じゃじゃ馬」と評されることもあります。
しかし、そのじゃじゃ馬を最も巧みに乗りこなす方法こそが、ハイボールなのです。ハイボールにすることで、ホワイトが秘めていたポテンシャルが最大限に引き出され、その評価は一変します。
むしろ、ハイボールで飲むことを前提に設計されているのではないかと思えるほど、素晴らしい相性を見せるのです。
その理由は、炭酸がホワイトの持つ長所を際立たせ、同時に短所を巧みにカバーしてくれるからです。
まず、炭酸の持つ爽快感ときめ細やかな泡が、口当たりをシャープに感じさせるアルコールの刺激的な香味を優しく包み込み、和らげてくれます。
これにより、ストレートでは感じられたピリピリとした刺激が影を潜め、驚くほどマイルドでスムーズな飲み口に変化します。
さらに、炭酸の泡がグラスの中で弾けるたびに、それまで奥に隠れていた黒蜜やカラメルのような甘い香りが、ふわりと立ち上ります。
味わいにおいても、炭酸が加わることで甘みがより一層引き立ち、爽やかなキレも生まれるため、食中酒としても素晴らしいパフォーマンスを発揮します。
まさに、炭酸がホワイトというウイスキーの「最高のパートナー」として機能するのです。
最高のホワイトハイボールを作るための手順
せっかくなら、その魅力を最大限に引き出す美味しいハイボールを作りたいものです。
サントリーが推奨する基本の作り方を、いくつかのポイントを加えてご紹介します。
(出典:サントリー ウイスキーのおいしい飲み方 ハイボール)
1:グラスを徹底的に冷やす
まず、主役となるグラスを冷凍庫でキンキンに冷やしておきます。
これが、氷が溶けにくく、最後まで味が薄まらないハイボールを作るための最初の重要なステップです。
2:氷を山盛りに
冷えたグラスに、市販のロックアイスのような硬く溶けにくい氷を、縁から少しはみ出すくらいまでたっぷりと入れます。
3:ホワイトを注ぎ、ステアする
ホワイトを適量(30ml〜45mlが目安)注ぎ、マドラーで10回以上しっかりと混ぜてウイスキー自体をよく冷やします。
ここで一度溶けた分の氷を足すと、さらに味が安定します。
4:ソーダを静かに注ぐ
ここが最も大切なポイントです。
グラスを少し傾け、冷えた強炭酸のソーダを氷に当てないように、グラスの縁から静かに注ぎ入れます。
炭酸が抜けないようにすることが、爽快なのどごしに直結します。
黄金比率は、ウイスキー1に対してソーダを3〜4の割合です。
5:混ぜるのは一度だけ
ソーダを注ぎ終えたら、マドラーをグラスの底まで静かに入れ、氷を少し持ち上げるようにして縦に一度だけ混ぜます。
ぐるぐるとかき混ぜてしまうと炭酸が抜けてしまうため、厳禁です。
仕上げに、レモンの皮を軽くひねって香りだけを移す「レモンピール」を施すと、柑橘の爽やかな香りが加わり、ホワイトの甘みと絶妙にマッチします。
また、少し甘めに楽しみたい場合はジンジャーエールやコーラで割るのもおすすめです。
ぜひ、ご自身の「最高の飲み方」を見つけてみてください。
サントリー ホワイト ウイスキー 40度 640ml
結論:まずいと言われたホワイトの楽しみ方
この記事では、サントリーホワイトにまつわる「まずい」という噂の真相から、その歴史、味わいの特徴、そして現在の楽しみ方までを多角的に解説してきました。
最後に、本稿の重要なポイントをまとめます。
記事のポイント まとめです
- サントリーホワイトに「まずい」という噂があったのは事実
- その主な理由は発売当初の強いスモーキーさに起因する
- 現在の製品は日本人の味覚に合わせ改良され飲みやすくなっている
- 日本初の本格国産ウイスキーとしての重要な歴史的価値を持つ
- ストレートではアルコールの刺激を強く感じる場合がある
- 一方で黒蜜やカラメルを思わせる独特の甘みが最大の特徴
- 「角瓶」に比べると香りは控えめで素朴な味わい
- 「レッド」よりは香味に厚みがありまろやか
- 終売の噂は誤りで現在も広く安定して販売されている
- 1,000円前後から購入できコストパフォーマンスに優れる
- 品薄のシングルモルトとは異なり日常的に入手しやすい
- このウイスキーの最高の楽しみ方はハイボールである
- 炭酸で割ることで香味のバランスが劇的に向上する
- レモンなどの柑橘類を加えるアレンジも相性が良い
- 歴史を知り飲み方を工夫すれば十分に楽しめる個性的な一本
【参考情報一覧】
・サントリーの歴史|企業情報: https://www.suntory.co.jp/company/history/timeline/
・サントリーウイスキーホワイト 製品紹介: https://www.suntory.co.jp/whisky/products/0000000038/0000000120.html
・サントリーウイスキー角瓶 製品紹介: https://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/
・サントリー ウイスキーのおいしい飲み方 ハイボール: https://www.suntory.co.jp/whisky/beginner/drink/highball.html
・SUNTORY WHISKY 山崎55年 公式サイト: https://www.suntory.co.jp/news/article/13651.html
・e-Gov法令検索 酒税法: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000006
・ぴろのウイスキーブログ まずい?サントリーホワイトをレビュー!: https://www.piroriro.com/entry/white-review
・ラマスピリッツ レビュー|サントリーウイスキー ホワイト: https://rama-spirits.com/review/suntory-white/
・You-Whisky.com サントリーウイスキー ホワイト【レビュー】: https://you-whisky.com/2021/04/01/suntory-white/
・なもなきアクアリウム 【レビュー】#164『サントリーウイスキー ホワイト』: https://asgsn.hatenablog.com/entry/2024/04/24/190000
/関連記事 琥珀色に輝く液体が重厚なグラスの中で揺れる、その芳醇な香りと共に静かな時間が流れていく…。 そんな光景に、一度は心を惹かれた経験はありませんか。 ウイスキーの世界は、ただのお酒という言葉 ... 続きを見る 「ハイボールを頼んだらウイスキーが出てきた」「ウイスキーとハイボールって何が違うの?」バーや居酒屋で、このような疑問を持った経験はありませんか。 この記事では、まずは基本か ... 続きを見る

関連記事ウイスキー好き必見!魅力と基本からおすすめ銘柄まで解説

関連記事ウイスキーとハイボールの違いとは?定義から作り方まで解説
